キッチンや寝室でタブレットを使いたいけれど、置き場所や配線、落下が心配でそのままにしていませんか。
専用の壁掛け器具は高価だったり賃貸だと取り付けに迷ったりと、意外とハードルが高いものです。
この記事では100均で揃うアイテムを使ったタブレットの壁掛けを、固定面別の取り付け方法や耐荷重、配線・防水対策まで実例を交えて分かりやすく紹介します。
工具不要の作例や賃貸向けの原状回復対策、落下防止のコツも載せているので、まずは手順と必要アイテムをチェックして自分に合う方法を見つけてください。
100均で実現するタブレットの壁掛け手順

身近な100均アイテムだけで安全にタブレットを壁掛けするための実用的な手順をまとめました。
各ステップは少しの準備と確認で完了できる内容にしています。
採寸
タブレット本体の縦横のサイズと厚みを正確に測ってください。
ケースを付けたまま使う場合はケース込みの寸法を測るのを忘れないでください。
-
メジャー、定規、またはノギスがあると測定が楽になります。
-
設置場所の有効スペースも合わせて測っておくと配置がスムーズになります。
-
複数台を壁掛けする場合は各機器ごとにサイズを控えておくと便利です。
重量確認
タブレットの重さを量るか仕様書で確認してください。
100均の粘着フックやホルダーは耐荷重に差があるので必ず確認が必要です。
|
タブレットサイズ |
目安重量 |
推奨耐荷重 |
|---|---|---|
|
7〜8インチ |
約200〜350g |
500g以上を推奨 |
|
9〜10インチ |
約400〜600g |
800g以上を推奨 |
|
11インチ以上 |
約600g〜800g以上 |
1kg以上を推奨 |
位置決め
画面の見やすさとケーブルの取り回しを考えて高さと角度を決めてください。
キッチンやリビングなど使用シーンごとに最適な位置が変わります。
人がよく通る場所や水回りの近くは避けると安全です。
下地確認
壁の素材を確認して取り付け方法を選んでください。
石膏ボードの場合は下地(間柱)があるかどうかを必ずチェックしてください。
賃貸の壁や仕上げ材によっては粘着タイプの方が安心な場合もあります。
マーキング
設置位置にマスキングテープなどで仮止めし水平を出してください。
水平器があると正確に位置決めできます。
鉛筆で薄く印を付けると取り付け作業が楽になります。
固定具の取り付け
100均で揃う粘着フックやネジ式のフックを使い分けてください。
粘着タイプは貼り付け面をきれいに拭き乾燥させてから貼ってください。
ネジで固定する場合は下地に合わせたアンカーやビスを用意してください。
ホルダーの設置
タブレット用のホルダーを壁に取り付けます。
ホルダーが100均で手に入る場合もありますが耐久性を確認してください。
ホルダーの角度調整ができるタイプなら見やすい角度に調節してください。
ケーブル配線
充電ケーブルやイヤホンの配線は邪魔にならないようまとめてください。
100均のケーブルクリップや結束バンドを使うとスッキリします。
電源タップの位置や長さに余裕を持たせて安全に配線してください。
安定性チェック
取り付け後に軽く押してぐらつきがないか確認してください。
数日間は時々チェックして粘着の剥がれやネジの緩みがないか確認するのがおすすめです。
不安がある場合は耐荷重の高い金具や専門の取付けに切り替えてください。
100均で揃うタブレット壁掛けアイテム

手軽にそろう100均アイテムだけでタブレットの壁掛けができるアイデアを紹介します。
賃貸でも工事不要で使える方法が多く、コストを抑えたい方にぴったりです。
粘着フック
粘着フックは貼ってはがせるタイプが多く、壁を傷つけにくい特徴があります。
タブレット用ホルダーや筒状のスタンドと組み合わせると簡単に壁掛けできます。
耐荷重を必ず確認して、タブレット本体の重さとケース込みの重さに余裕を持たせてください。
石膏ボード用ピン
石膏ボード用ピンは軽量のタブレットを確実に支えるのに向いています。
ピンの打ち込み位置を慎重に選んで、コンセントや配線を避けて使用してください。
賃貸の場合は管理規約を確認してから使用することをおすすめします。
マグネットシート
マグネットシートは金属製の家具や磁石が使える壁面に便利です。
タブレットケースの背面に貼っておけば簡単に着脱できます。
磁力が弱い場合は複数枚重ねるか、マグネット強度の強い商品を選んでください。
面ファスナー
面ファスナーは仮止めや取り外しが多い場所に向いています。
片面を壁に貼り、もう片面をタブレットケースに貼るだけで着脱が簡単です。
頻繁に外すと粘着力が落ちることがあるので、耐久性を確認して使ってください。
タブレットスタンド
100均の折りたたみスタンドを壁掛け用に転用する方法があります。
粘着フックやワイヤーネットと組み合わせて固定すれば省スペースで使えます。
角度調整できるタイプを選ぶと視線に合わせやすく便利です。
ワイヤーネット
ワイヤーネットは壁面収納として応用しやすいアイテムです。
ネットにフックや結束バンドでスタンドを固定すれば安定した壁掛けができます。
- キッチンでレシピを見る用途。
- リビングで動画視聴する用途。
- 子ども部屋で学習用に使う用途。
結束バンド
結束バンドは簡単に固定できて耐久性もあるので補強に便利です。
ワイヤーネットやフックと組み合わせてタブレットを落ちにくくできます。
切断時は切り口が鋭利になることがあるので丁寧に処理してください。
滑り止めパッド
滑り止めパッドはタブレットのズレを防ぐための小物として優秀です。
タブレットと固定具の間に挟むだけで振動や落下のリスクを下げられます。
サイズや厚さで使い勝手が変わるため確認してから購入してください。
| タイプ | 厚さ | おすすめ設置箇所 |
|---|---|---|
| シートタイプ | 1〜2mm | ケース裏面やスタンド底面 |
| ジェルタイプ | 3〜5mm | 壁と接する面のクッション用 |
| スポンジタイプ | 5mm以上 | 隙間がある取り付け箇所の調整用 |
耐震ジェル
耐震ジェルは地震対策としてタブレットを固定するのに役立ちます。
透明なタイプが多く目立ちにくいのも利点です。
粘着力が落ちたら交換して安全性を保ってください。
ケーブルクリップ
ケーブルクリップは充電ケーブルの落下や引っかかりを防ぎます。
壁掛けしたタブレット周りをすっきりまとめられて見た目も良くなります。
強粘着タイプを選ぶと長時間の使用でも外れにくいです。
壁掛けの固定面別取り付け方法

壁の素材によって使う金具や接着剤が変わるため適切な方法を選ぶことが大切です。
タブレットを安全に壁掛けするために強度や取り外しのしやすさを意識して選んでください。
石膏ボード
石膏ボードは内部が空洞になっているタイプが多く、直接ネジを打つだけでは抜けやすいです。
軽い取り付けには粘着フックや100均の両面テープタイプも使えますが耐荷重に注意してください。
重さがあるタブレットを長期間掛ける場合は専用のアンカーやボードアンカーを使うのが安全です。
-
ステップ1として取り付け箇所の裏側に下地があるか確認してください。
-
ステップ2としてボード用アンカーを選び、取扱説明に従って取り付けてください。
-
ステップ3としてブラケットや金具で荷重を分散させると落下リスクを減らせます。
タイル
タイル面は硬くて割れやすいため、取り付け方法の選択に注意が必要です。
タイルに直接ドリルで穴を開ける場合はタイル用のドリルビットを使い、周囲を保護して慎重に作業してください。
タイルの目地部分に取り付けるとタイル自体を避けられて安全なことがあります。
|
方法 |
メリット |
デメリット |
100均での対応 |
|---|---|---|---|
|
ドリル+アンカー |
強固で長期間の使用に向く |
タイル割れのリスクと工具が必要 |
アンカーはホームセンター推奨で100均は不安 |
|
強力両面テープ |
簡単で工具不要 |
接着力が環境で変わるため耐久性に限界がある |
100均のテープは短期利用向けのことが多い |
|
吸盤・サクションタイプ |
穴を開けないのでタイルを傷めない |
時間経過で外れやすい場合がある |
100均の吸盤は強度が弱い場合があるので注意 |
木材
木の壁や下地がある場合はネジ止めが基本で最も安定します。
下穴をあけてからビスを入れると割れを防げます。
金具やブラケットを使えば荷重を分散できるためタブレットを安心して掛けられます。
100均の金具は軽量のタブレットや短期利用なら使えることがありますが、耐荷重表示を必ず確認してください。
金属
金属面には自己タッピングビスやタッピングスクリューが有効です。
薄い金属板の場合はナットとボルトで挟む方法や強力磁石での固定を検討してください。
磁石で固定する場合は壁の素材が磁力を受けるかを確認する必要があります。
100均の磁石やフックは強力でないものが多いため、重さのあるタブレットには適さないことがあります。
ガラス
ガラス壁やガラス扉に取り付けるときは穴あけは極力避けるべきです。
吸盤式のホルダーやクランプ式の金具を使う方法が高リスクを避けられます。
ガラスに接着する場合は専用のガラス用接着剤や強力両面テープを使い、取り付け前に表面の油分をしっかり拭き取ってください。
100均の吸盤や粘着パーツは短期間の利用や軽量タブレット向けとして試せますが長期の安全性は保証されない点に注意してください。
タブレット壁掛けの設置場所別活用シーン
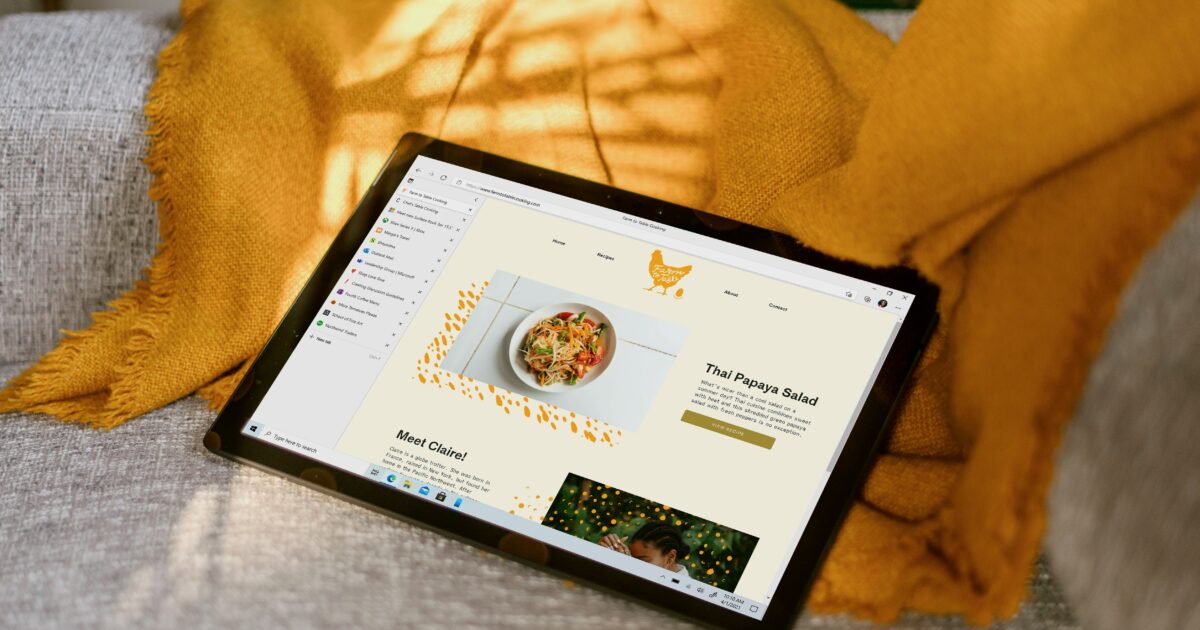
タブレットを壁掛けにすると視線の位置が安定して両手が空くメリットがあります。
100均アイテムを活用すると低コストで工夫できるのが魅力です。
キッチン
キッチンではレシピ表示や動画で手順を確認しながら作業できます。
100均の粘着フックやスマホホルダーを利用して壁に固定する方法が手軽です。
油や水はねが気になる場所では防水ケースやクリアファイルでカバーするのが効果的です。
-
セリアやダイソーのタブレットスタンドは角度調整ができて便利です。
-
粘着タイプのフックは繰り返し使うと剥がれやすいので補強を検討してください。
-
ケーブルはクリップや結束バンドでまとめて調理中の邪魔を防ぎます。
洗面所
洗面所ではニュースや音楽を流しながら身支度ができます。
ミラー横のスペースに粘着フックで設置すると目線に合わせやすいです。
湿気対策としてはジップロックや防水シートを併用してください。
浴室
浴室での使用は防水性能の高いケースや防滴仕様のタブレットを選ぶ必要があります。
100均の吸盤フックは手軽ですが、タブレットの重さに耐えられない場合があるためサイズや耐荷重表示を確認してください。
電源ケーブルを浴室内で扱うと感電の危険があるため、バッテリーでの使用を推奨します。
寝室
寝室では映画や電子書籍を枕元で楽しめるように設置すると快適です。
壁掛けアームや角度調節可能なブラケットを使うと姿勢負担が減ります。
100均の柔らかいクッション素材を併用してタブレットと壁の接触部分を保護してください。
玄関
玄関にタブレットを設置すると天気予報やスケジュール確認がスムーズになります。
薄型のホルダーやマグネットタイプを使うと出かける前のチェックが楽になります。
充電ステーションを兼ねる場合はケーブルをまとめて転倒やつまずきの原因を減らしてください。
リビング
リビングではフォトフレーム代わりに使ったり、スマートホームの操作パネルに活用できます。
複数人で見る場合は視野角の広い位置に設置するのがおすすめです。
下表は代表的な壁掛け方法と100均で揃うアイテムの比較です。
|
設置方法。 |
100均アイテム例。 |
メリット。 |
注意点。 |
|---|---|---|---|
|
粘着フック固定。 |
粘着フック、粘着シート。 |
取付が簡単で目立ちにくい。 |
耐荷重が低い場合がある。 |
|
吸盤設置。 |
吸盤フック、吸盤ホルダー。 |
壁に穴を開けずに設置できる。 |
湿気や温度変化で外れることがある。 |
|
ネジやブラケットでの固定。 |
金具類は100均にない場合があるが小型ブラケットは見つかることがある。 |
安定性が高く長期利用向き。 |
壁に穴を開ける必要がある。 |
仕事部屋
仕事部屋ではサブモニターやスケジュール確認ツールとして活用できます。
目線の高さに合わせて設置すると首や肩の負担が減ります。
ケーブル管理には100均のケーブルボックスや結束バンドが役立ちます。
長時間使用する場合は角度調整と明るさ調整で目の疲れ対策を行ってください。
タブレット壁掛けの耐荷重の考え方
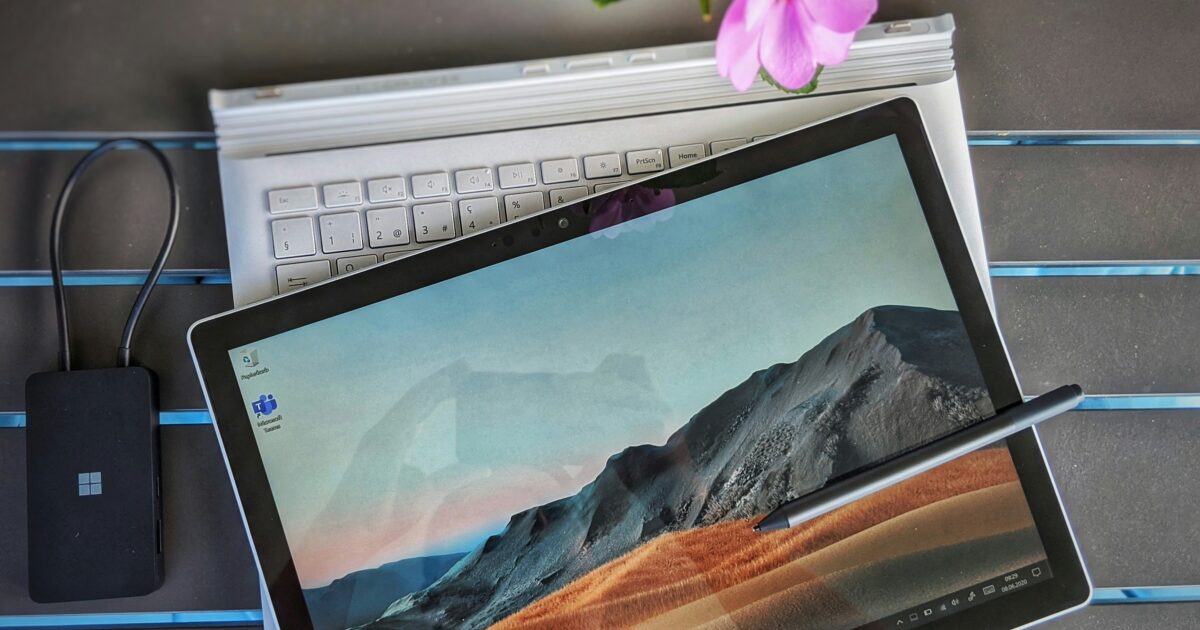
タブレットを壁に掛ける際は耐荷重の見方を押さえておくと安心感が増します。
特にタブレット 壁掛け 100均のアイテムを使う場合は、公称値と実際の使い方の差を考慮することが重要です。
設置場所や素材によって想定以上の力がかかることがあるため安全側で考える習慣が役立ちます。
公称耐荷重
公称耐荷重とはメーカーや販売元が表示する最大荷重のことです。
この数値は試験条件下の理想的な環境で測定された値であることが多いです。
100均の製品はコスト優先の設計が多く、公称値が記載されていても余裕が小さい場合があります。
実効耐荷重
実効耐荷重は実際にその場所や取り付け方で耐えられる荷重のことです。
実効耐荷重は表記の公称耐荷重より小さくなることが一般的です。
-
接着面の状態は大きく影響します。
-
温度や湿度で粘着材の性能が変わります。
-
取り付け角度や振動などの動的負荷も考慮する必要があります。
-
タブレット自体の形状や重心位置が影響します。
安全率
安全率とは想定荷重に対してどの程度の余裕を持たせるかを示す比率です。
家庭でのタブレット壁掛けでは最低でも安全率2倍を目安にするのが無難です。
例えばタブレットの重量が500グラムならば公称耐荷重が1キログラム以上あるか確認すると安心です。
衝撃や落下のリスクがある場所ではさらに高い安全率を検討してください。
粘着力低下
粘着ジェルや両面テープは時間経過で粘着力が低下することがあります。
ホコリや油分、表面の凹凸は初期の接着力を妨げます。
定期的に取り付け部を点検し、違和感があれば交換や補強を検討してください。
100均の粘着製品は比較的安価で交換がしやすい反面、耐久性に限界がある点を覚えておきましょう。
面圧
面圧は荷重を接触面積で割った値で、接着剤やフックにかかる局所的な負荷を示します。
同じ重量でも接触面積が小さいほど面圧は高くなり、剥がれやすくなります。
面圧を下げるには接触面積を増やすか荷重を分散させる工夫が有効です。
|
接触面積の目安 |
面圧のイメージ |
向く用途 |
|---|---|---|
|
小さめ(約20cm²) |
高めで剥がれやすい。 |
軽量の小物向け。 |
|
中くらい(約50cm²) |
中間で安定しやすい。 |
小型タブレットや軽めのケース向け。 |
|
大きめ(約100cm²) |
低めで安定しやすい。 |
重量があるタブレットや長期設置向け。 |
取り付け面が平滑であるほど均等に面圧を分散しやすくなります。
可能であれば接着面を広く確保するか、フックやプレートで荷重を分散する工夫をしましょう。
タブレットサイズに合わせた壁掛けホルダー選定
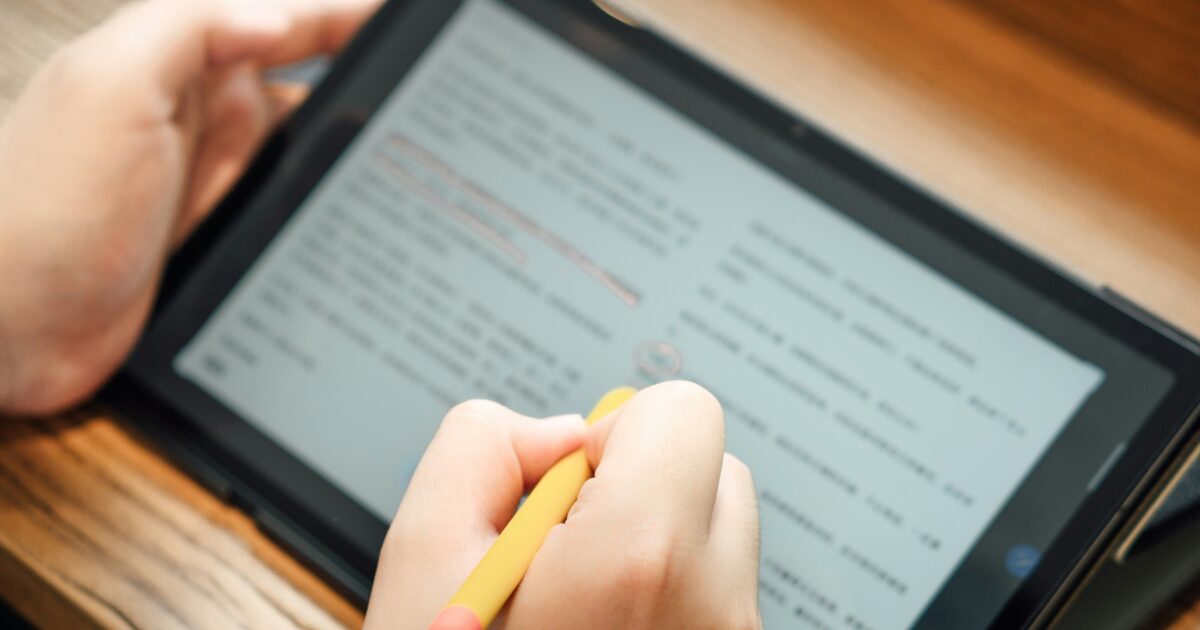
タブレットのサイズに応じて選ぶべき壁掛けホルダーは変わります。
安全性と利便性を両立できるアイテムを中心に選ぶと失敗が少ないです。
7〜8インチ
7〜8インチのタブレットは軽量で扱いやすいため100均アイテムでも十分対応できます。
粘着タイプのフックやシリコーン製のスマホスタンドを組み合わせると安定感が出ます。
短所としては強い衝撃や長期間の負荷で粘着力が落ちる点に注意が必要です。
-
透明な吸盤フックを使うと壁面を傷つけずに取り付けられます。
-
スマホ用の落下防止リングを背面に貼ってフックに引っかける方法が手軽です。
-
ワイヤーやケーブルクリップで充電ケーブルを固定すると使い勝手が良くなります。
-
キッチンで使うなら耐熱性や油はねに強い素材を選びましょう。
取り付け前にタブレットの重さと粘着フックの耐荷重を必ず確認してください。
9〜11インチ
このサイズは中重量のため取り付け方法を慎重に選ぶのが重要です。
100均で手に入る部品を組み合わせて自作できる場合もありますが、強度確認は必須です。
|
アイテム |
メリット |
注意点 |
|---|---|---|
|
金属製のミニ棚(小物用) |
安定して置けるため落下リスクが低いです。 |
壁への固定が甘いと棚ごと外れる恐れがあります。 |
|
粘着式のタブレットスタンド |
取り外しや角度調整が簡単です。 |
長期間使用で粘着力が低下することがあります。 |
|
クリップ式ホルダー(多用途) |
厚さ調整ができて多様な機種に対応できます。 |
挟み込み部の滑り止めがないと表面に傷がつくことがあります。 |
テーブルの内容を参考にして自分の使い方に合うアイテムを選んでください。
角度調整や充電がしやすい配置を優先すると日常使用がぐっと楽になります。
12インチ以上
12インチ以上の大型タブレットは重量が増すため100均の単体アイテムだけで支えるのはリスクがあります。
強度を高めるために壁の下地にアンカーやネジでしっかり固定する補助を検討してください。
アイテム選びとしては金属ブラケットや小さな飾り棚をベースに補強材を併用する方法が現実的です。
設置場所は落下による怪我や破損リスクを考慮して人通りの少ない場所や子どもの手の届かない位置を選びましょう。
充電やスピーカー利用を妨げない向きで取り付けることと、定期的にネジや接着部の緩みを点検する習慣をつけてください。
大型機は市販の専用マウントやプロの取り付けを検討するのが安心です。
賃貸で使う100均の壁掛け原状回復対策

タブレット 壁掛け 100均のアイテムを使って賃貸でも壁に跡を残さない工夫を紹介します。
軽量のタブレットやケース付きのものを前提に、安全で取り外しやすい方法を中心に説明します。
再剥離テープ
再剥離タイプの両面テープは壁紙を傷めにくく跡が残りにくい点が魅力です。
貼る前に壁の汚れやホコリをしっかり拭き取ると粘着が安定します。
耐荷重の目安を守り、タブレットの重さがテープの許容範囲内か確認してください。
取り外すときはゆっくり引き離し、熱を加えると剥がしやすくなります。
極細ピン
極細ピンは小さな穴で済むため原状回復がしやすい方法です。
-
薄い壁紙やビニールクロスには細い画鋲タイプが使いやすいです。
-
下地が合板や石膏ボードの場所を選ぶと抜けにくく安心です。
-
位置決めは水平器やマスキングテープで仮止めしてから行うとズレません。
長時間使用する場合はピンの本数を増やして荷重を分散させてください。
マグネット
マグネットを使う方法は金属下地がある場所で特に有効です。
|
タイプ |
取り付け跡 |
耐荷重の目安 |
備考 |
|---|---|---|---|
|
ネオジムマグネット |
基本的に跡は残りません。 |
小型タブレットなら十分な保持力があります。 |
強力なので取り外し時に手を挟まないよう注意してください。 |
|
マグネットフック |
金属面に直接掛けるだけで跡は残りません。 |
耐荷重はフックの種類で変わります。 |
金属面がない場合はプレートを両面テープで貼ると使えます。 |
|
両面テープ付きマグネット |
テープ部分の跡に注意が必要です。 |
軽めのタブレット向けです。 |
貼る面の材質を確認してから使ってください。 |
金属がない壁でもプレートを使えば磁石式の設置が可能です。
養生シート
養生シートは取り付け作業中に壁を保護するために使います。
テープ跡が不安な場合はまず養生シートを壁に貼り、その上に固定具を取り付けると安心です。
シートは100均でも手に入り、余分な力が一点に集中するのを防げます。
取り外すときはシートをゆっくり剥がして壁の状態を確認してください。
保護フィルム
タブレット本体の保護だけでなく壁との接触面に薄いフィルムやクッション材を挟むと傷を防げます。
100均の透明フィルムや滑り止めシートを適当な大きさに切って使うと目立ちにくいです。
貼る位置にずれ防止のガイドをつけておくと設置が安定します。
必要なときだけ貼って使い、不要になったら交換や剥がしが簡単にできるものを選ぶと便利です。
タブレット壁掛けの落下防止アイデア

タブレットを壁掛けで使うときは落下対策をしっかり行うことが大切です。
特に100均アイテムを活用すると低コストで安全性を高められます。
二重フック
二つのフックでタブレットを支えると万が一片方が外れても落下を防ぎやすくなります。
左右に並べるタイプか上下で支えるタイプを選ぶと安定性が違います。
100均の金具フックを使う場合は耐荷重表示を確認して余裕を持った選び方をしてください。
取り付けは石膏ボード用のアンカーや強力な粘着パッドと組み合わせると効果的です。
滑り止めシート
滑り止めシートを接触面に貼ることでズレや落下のリスクを減らせます。
|
種類 |
厚さの目安 |
特徴 |
100均での入手感 |
|---|---|---|---|
|
シリコンタイプ |
約1〜3mm。 |
グリップ力が高く耐久性も良いです。 |
見つかりやすく手軽に使えます。 |
|
EVAフォーム |
約2〜5mm。 |
クッション性があり衝撃吸収に優れます。 |
バリエーションは限定的ですがあります。 |
|
ゴムシート |
約1〜4mm。 |
摩擦係数が高く滑りにくいです。 |
店舗によっては取り扱いがない場合があります。 |
貼り付ける前にホコリや油分を拭き取ると粘着が安定します。
ストラップ固定
ストラップで本体を固定すると落下しても本体が宙に留まるので破損リスクが下がります。
100均の幅広バンドや結束用のテープを活用すると簡単に取り付けられます。
-
両端をフックにかけるタイプは重さが分散されます。
-
背面に輪を作ってタブレットをはめ込む方法は着脱が楽です。
-
伸縮性のあるストラップを選ぶと振動や衝撃を和らげます。
穴開けが不安な場合は粘着パッチや面ファスナーと組み合わせると安心です。
落下距離制限
落下距離を短くすることで地面に衝突したときの衝撃を抑えられます。
短いチェーンや伸縮コードを使ってタブレットの最大落下距離を制限してください。
壁から離れた位置にクッション材を置くことで最悪の衝撃を和らげられます。
高さを決めるときは使用時の角度やケーブルの取り回しも考慮しましょう。
定期点検
定期的に固定具や粘着剤の状態を確認すると早めに不具合に気づけます。
目安は月に一度程度で、ホコリの付着や接着面の劣化がないかチェックしてください。
緩みや亀裂が見つかったらすぐ交換することで事故を未然に防げます。
100均の消耗品は手軽に買い替えられるので古くなったら躊躇せず交換しましょう。
壁掛け中のタブレットの配線整理

壁掛けしたタブレットの見た目は配線の整理で大きく変わります。
100均アイテムを活用するとコストを抑えつつ見た目と使い勝手を両立できます。
配線は安全面にも関わるため、固定方法や導線の取り回しに気を配ることが大切です。
ケーブルクリップ
ケーブルクリップは配線を壁沿いに固定して目立たなくする基本アイテムです。
100均では粘着タイプや差し込みタイプ、挟むタイプなどが揃っています。
-
粘着タイプは貼るだけで手軽に使えますが、貼付面の油分を拭き取ってから貼ると剥がれにくくなります。
-
差し込みタイプは薄いケーブルに向いており、複数本まとめるときに便利です。
-
挟むタイプは太めのケーブルやコネクタ部分の固定に強くおすすめです。
クリップを等間隔に配置すると見た目が整いやすくなります。
ケーブルに無理な曲げを作らないよう、クリップは余裕を持たせて固定してください。
ケーブルモール
ケーブルモールは複数本のケーブルをまとめて隠せるため見た目がすっきりします。
|
種類 |
特徴 |
取り付けのしやすさ |
耐久性 |
価格目安 |
|---|---|---|---|---|
|
粘着タイプモール |
裏面が粘着テープで貼るだけで簡単に設置できます。 |
非常に簡単です。 |
短期利用なら十分ですが、負荷の強い場所は注意が必要です。 |
100均で手に入ります。 |
|
スナップ式モール |
蓋を開け閉めできて配線の出し入れが楽です。 |
少し手間がかかりますが再利用しやすいです。 |
蓋の耐久性は商品によります。 |
100均でも見つかることがあります。 |
|
コーナー用モール |
壁の角や天井付近に沿わせやすい形状です。 |
位置合わせが重要です。 |
取り付けがしっかりしていれば安定します。 |
100均で扱っている場合があります。 |
モールを使うと掃除もしやすくなり見た目の印象も良くなります。
モールを貼る前に壁面の汚れを拭き取りしっかり乾かしてください。
巻き取り
余ったケーブルは適度に巻き取っておくとだらしなく見えません。
100均のコードバンドやマジックバンドは巻き取りに最適です。
巻き取りグッズがない場合は柔らかい布バンドやゴムバンドで代用できます。
巻きすぎるとケーブル内部が痛むのでループは大きめに取るのがコツです。
可動部分があるならコネクタ近くに余裕を残しておくと断線を防げます。
ACアダプタ固定
タブレット充電用のACアダプタは大きさで目立ちやすいためしっかり固定すると見た目が良くなります。
100均の粘着フックやワイヤーフックを組み合わせてアダプタを壁面近くに固定できます。
粘着力に不安がある場合はネジ止めタイプや結束バンドで補強してください。
アダプタは放熱のために少し空間を空けて固定するのが安全です。
接続点に負荷がかからないようケーブルを緩ませて取り回してください。
延長コード
タブレットの位置にコンセントが近くにない場合は延長コードを使って電源を引き寄せると便利です。
100均の延長コードは手軽ですが定格電流を確認して安全に使用してください。
延長コードは長すぎると絡まりやすいので必要最小限の長さを選んでください。
延長コード自体を壁に沿わせるときは前述のケーブルクリップやモールで固定するとすっきりします。
複数の電気機器を同じ延長コードに集中させないようにし、過負荷を避けてください。
キッチン向けのタブレット壁掛けの水濡れ対策

キッチンでタブレットを壁掛けする際は水濡れ対策を優先して考えることが大切です。
100均のアイテムをうまく使うとコストを抑えつつ実用的な対策ができます。
ここでは簡単に取り入れられる具体的な方法を紹介します。
防水ケース
防水ケースは直接水がかかるのを防ぐもっとも手軽な方法です。
専用品は密閉性が高くタッチ操作に対応したものもありますが価格がやや高めです。
100均のジップロック系の大きな袋を使うと安価に代用できますが、タッチ感度や見やすさが落ちる場合があります。
壁掛け時はケースの上部をしっかり固定して下部に水がたまらないよう角度をつけると効果的です。
長時間の使用や高温多湿の場所ではケース内に湿気がこもることがあるため、定期的に取り外して乾燥させる習慣をつけましょう。
撥水フィルム
画面の撥水フィルムは小さな水滴を弾いて拭き取りやすくします。
100均で手に入るフィルムはコストパフォーマンスが良い反面、耐久性や指滑りに差があります。
貼り付けの際は気泡を防ぐことが重要です。
-
表面のホコリをきれいに取り除いてから貼ること。
-
位置を合わせたら一端からゆっくり貼り付けて気泡を押し出すこと。
-
エッジから浮きが出たら専用のヘラか柔らかい布で平らにすること。
-
貼付後は数時間放置して接着剤を定着させること。
タッチレスポンスが落ちる場合は厚手のフィルムより薄手を選ぶと快適になります。
防滴カバー
防滴カバーはスプレーや蒸気といった広範な水分からタブレットを守ります。
透明な塩化ビニールやアクリルで作られたカバーは見た目もすっきりします。
100均素材で自作する場合は固定方法と通気性に注意してください。
|
方法 |
防水性能 |
価格目安 |
100均で入手可否 |
|---|---|---|---|
|
専用防水ケース |
高 |
中〜高 |
部分的に可 |
|
ジップロック等の袋 |
中 |
低 |
可 |
|
自作アクリルボックス |
中〜高 |
中 |
一部材料可 |
テープや両面テープで壁に固定する場合は剥がれにくい素材を選びましょう。
結露対策
キッチンは調理による蒸気で結露が発生しやすい場所です。
壁掛けの際はタブレットと壁の間に少し隙間を作り空気の流れを確保すると結露を抑えられます。
100均で手に入るシリカゲルや乾燥剤をケース内に入れておくと湿気吸収に役立ちます。
レンジや鍋の近くには設置しないか、遮熱プレートやシールドを挟んで直接の蒸気を避けてください。
定期的にカバーを外して内部の湿気をチェックする習慣をつけるとトラブルを未然に防げます。
乾燥時間
水に触れた場合はすぐに柔らかい布で拭き取ることが基本です。
防水ケースに入れていた場合でも、長時間放置すると内部に湿気が残ることがあるため取り出して乾燥させてください。
軽い水は布で拭いた後、風通しの良い場所で1〜2時間乾かすと安全です。
内部に水が入り込んだ疑いがある場合はケースを開けて完全に乾くまで24時間程度置くのが望ましいです。
ドライヤーを使うときは低温設定で距離を取りながら短時間ずつ行ってください。
乾燥剤は交換時期を守り、繰り返し使う場合は天日で再生するか交換用を用意しておくと安心です。

